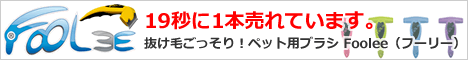猫の日本史:猫を驚かせた犬は、なぜ”島流し”になったのか

前回からまた間が空きましたが、細く長く続きます。
源氏物語と並ぶ平安文学の代表作品といえば、おなじみ清少納言の『枕草子』です。そしてそこには、日本史上最古の部類の「呼び名のついた猫」の話が記されています。ちょっと長くなりますが、『新編 日本古典文学全集』(小学館)から『枕草子』第7段の冒頭部分を以下に引用します。
『枕草子』の猫逸話「命婦のおとど」と「翁まろ」
上に候ふ御猫は、かうぶりにて、命婦のおとどとて、いみじうをかしければ、かしづかせたまふが、端に出でて臥したるに、乳母の馬の命婦、「あな正無や。入りたまへ」と呼ぶに、日のさし入りたるに、ねぶりてゐたるを、おどすとて、「翁まろ、いづら。命婦のおとど食へ」と言ふに、まことかとて、痴れ者は走りかかりたれば、おびえまどひて、御簾の内に入りぬ。朝餉の御前に、上おわしますに、御覧じて、いみじうおどろかせたまふ。猫を御懐に入れさせたまひて、をのこども召せば、蔵人忠隆、なりなかまゐりたれば、「この翁まろ打ちてうじて、犬島へつかはせ、ただいま」と仰せらるれば、あつまり狩りさわぐ。馬命婦をもさいなみて、「乳母かえてむ。いとうしろめたし」と仰せらるれば、御前にも出でず。犬は狩り出でて、滝口などして、追ひつかはしつ。
(現代語訳)
主上(一条天皇)のおそばに伺候している御猫は、五位をいただくことによって、「命婦(みょうぶ)のおとど」ということになって、たいへんかわいいので、大切に世話をしておいであそばす、その猫が、縁先に出て横になっているので、お守役の馬の命婦が、「まあお行儀が悪いこと。お入りなさいまし」と呼ぶのだけれど、日がさしこんでいる所で、眠ってじっとしているのを、おどかすために、「翁(おきな)まろ、どうしたの。命婦のおとどに噛(か)みつけ」と言うと、本当かと思って、愚か者の翁まろは走って向っていったので、猫のおとどはこわがりうろたえて、御簾(みす)の中に入ってしまった。朝餉(あさがれい)の御前(おまえ)に、主上がいらっしゃった時で、御覧あそばして、たいへんびっくりあそばされる。猫をご自分の御ふところにお入れあそばして、殿上(てんじょう)の男の人たちをお呼び寄せになると、蔵人(くろうど)の忠隆(ただたか)となりなかが参上したので、「この翁まろを打ちこらしめて、犬島に追いやれ、今すぐ」とお命じあそばすので、集って、大さわぎをして追い立てる。主上は馬の命婦をもお責めになって、「守役をかえてしまおう。ひどく気がかりだ」と仰せになるので、馬の命婦は御前にも出ない。犬は狩り立てて、滝口(たきぐち)の武士などに命じて、追放なさってしまう。
簡単にまとめますと、引用部のストーリーはこのような内容です。
- 一条天皇が寵愛する「命婦のおとど」と呼ばれる飼い猫がいて、五位の官位を授けられ天皇の住まいで生活していた。
- ある日、縁側で猫が寝ているところへ、猫の御守役の女性「馬の命婦」が、冗談のつもりで、翁まろ(翁丸)という名の犬をけしかけた。
- 驚いた猫は御簾の中へ。逃げ込んだ場所にちょうど一条天皇が居合わせて、驚愕。自分の懐に猫を入れてかくまう。
- 天皇は蔵人たちへ、「翁まろを打ち懲らしめて、犬島へ追放!」と命令し、翁まろは追放される(正確には、されそうになる)。馬の命婦もお咎めをうけて御役目交代に。
この段の結末は、なんだかんだで、意外と皆からかわいがられていた翁まろが、お咎めを許されてハッピーエンドになりますのでご安心ください。
さて、犬島とは、近年の研究によれば「京都府南部の淀の中洲のひとつに犬を放逐する島」があり、それを指したと考えられています(『日本国語大辞典』犬島の項の語誌より)。犬にとってはまさに遠島島流し。命令に従っただけで、しかも未遂なのに大ごとになってしまいました。日向ぼっこ中に驚かされた猫と、飼い主たる一条帝の気持ちを、現代の私たち猫飼い主の身に即して想像してみると、そこまで怒るのも、まあ、無理なからぬ話だと感じる人のほうが多いかもしれません。
では、それをひもとくために、史料を使って”現場検証”を行うことといたしましょう。
事件の現場と、登場人物&動物の位置関係を探る
舞台となったのは、天皇が日常の生活を送った清涼殿の一画です。三省堂ワードワイズ・ウェブ「絵巻で見る 平安時代の暮らし 第35回」の清涼殿の平面図、およびデジタル大辞泉の清涼殿の平面図を参照すると、全体図が把握できます。「朝餉の間」は清涼殿の北東側にあり、簀の子を挟んで「朝餉の壺」という中庭に面しています。この部分には屋根がないため、日ざしが入ったわけです。
平面図を眺めていると、柱と間仕切りがあるだけだと誤解しかねませんので、より詳しく清涼殿を描いた「清涼殿之図」を用いて解説しましょう。国会図書館デジタルコレクションに所蔵されたこの図は、江戸時代に御厨子所預を務めた高橋宗直(1703〜1785)が、鎌倉期に成立した有職故実書『禁秘抄』や室町期の『禁腋秘抄』などを元に再現して描いたもので、その自筆図は京都府立京都学・歴彩館に所蔵されています。国会図書館所蔵の図は、明治に入って制作された複製と見られます。御厨子所預とは、天皇の朝夕の食事作りや節会などの酒肴を担当する地下官人で、いわば天皇の”台所番”です。そのため、天皇が日常的な食事をする朝餉の間の描写も詳しく描かれています。ただし、清涼殿は幾度も火災に見舞われた記録が残り、今回の話の舞台となる一条帝の時代のあとにも幾度となく火災に遭ったため、猫が眠っていたときの清涼殿とは異なっている可能性もあります。

一条帝が「朝餉の御前」(朝ご飯の前)にいたとき、翁まろにけしかけられた猫が御簾に入ったとありますから、猫がいたのは、清涼殿と後涼殿の間の中庭(=朝餉の壺)に面した簀の子の端で、翁まろがいたのも朝餉の壺の近くだと推察されます。翁まろは元々朝餉の壺にいたのか、または馬の命婦に呼ばれて切り馬道(殿と殿とを渡す板で、馬を壺に通すときには板を外して、馬の通り道にした)の下をくぐってきたのかもしれません。朝餉の間には『清涼殿之図』に記載のある通り、簀の子側には蔀が、屋内側に簾があります。蔀は上下2枚に分かれており、上の蔀だけをはねあげて垂木から吊していたと言いますので、このときも、下の蔀は填めこまれたまま、上の蔀だけが解放されていたのでしょう(実際の蔀の写真はこちらを参考になさると分かりやすいです)。となれば、犬から逃げた猫は「下の蔀を飛び越えて、御簾が垂れる屋内に逃げ込んだ」ことになります。
この猫と犬の騒動が起こったのは『新編 日本古典文学全集』の注釈によれば、諸記録から長保二年(1000年)の3月中旬と推定されています。朝餉の時間は、史料によって諸説ありますが、朝夕の2回で午前中に1回、夕刻に1回だったことは確かなようです。そこから考えると、猫が眠っていたのは、午前中の朝餉の最中で、日が高くなる午前11時頃だったのではないかと推察されます。旧暦の3月ですから、新暦に直せば、ちょうど4月の今ごろ。春の日ざしがポカポカと差し込む、絶好の日向ぼっこタイムだったものと考えられます。
「朝餉の間」および清涼殿の大きさは
朝餉の間の広さは2間×1間(図の「●」は柱を示し、その間隔は1間)。現在の1間は約180cm(畳の長辺=6尺)ですが、当時の1間は10尺(1丈)で、当時の1尺(曲尺)は現在とあまり変わらず約30cm。2間×1間の面積はだいたい18㎡になります。「6畳+バストイレのワンルームの床面積が、朝ご飯用のスペース」と考えるとそのサイズ感が伝わりやすいかと思います。
京都御所には、江戸時代の安政年間に復元された清涼殿があり(当時の図面は京都大学付属図書館に所蔵され、デジタルデータが公開されています)、GoogleMapsのストリートビューでその外観を確認できます。平面図でいうと、下側の「東庭」側の呉竹と川竹の間から、清涼殿を臨むかたちになります。朝餉の間や朝餉の壺のある西側とは逆の向きからの写真ですが、簀の子の高さや建物の大きさは確認いただけます。補足情報としては「十二世紀の清涼殿の柱間は多く一丈であったらしいが、現在のは桁行で七・五五尺、梁行で一〇尺、殿上の梁間は一五・一五尺である。つまり古代と比べて、桁行が縮小されているようである。」と国史大辞典の清涼殿の項にもあるように、現存の清涼殿は平安時代のものよりも少し小さいため、心の目で心もち大きな姿を想像していただければ幸いです。
現場検証を経た頭で、あらためてあの場面を思い起こして、そのときの描写を細かく記しますと、こうなるものと思われます。
- 正午前の日がさし来む、中庭(朝餉の壺)に面した簀の子の上で猫(命婦のおとど)が日向ぼっこをしていた。
- 馬の命婦がけしかけた犬(翁まろ)が、急に猫へ近寄って来たため、猫は慌てて逃げ出す。
- 逃げ出した猫は、朝餉の間の下蔀を飛び越えて、御簾の内側へ逃げ込む。
- ちょうど朝餉(朝ご飯)中だった一条帝のいる前に、猫が飛び込んでくる。一条帝は猫を懐にかくまう。
一条帝による厳しい対処の理由を考える
その後、前述のように蔵人や、警備の武士(滝口の武士)を使って犬を捕まえたり追放してしまいます。なぜそんなに厳しい態度にでる必要があったのか。その裏側には不安や恐れがあったと考えるのは、不自然ではないように思います。ではその不安と恐れとはなんでしょうか。それを考えてみると、次のような点が挙げられます。
- 猫の世話役の馬の命婦による”職務怠慢”
- 愛猫を驚かせて、怖がらせた点
- 食事の最中にトラブルを引き起こした点
- 一歩間違えれば、猫が逃げ出してしまいかねない点
清涼殿や内裏の大きさ・広さを見て気づくのが「猫が逃げて隠れたら、見つけるのは容易ではない」ということです。猫の性質が当時も今も変わらないのであれば、猫飼い主の最も大きな不安とは、やはり「行方不明」でしょう。しっかり戸締まりをしている現代の家屋でも、一瞬の隙を突いて外に抜け出して、帰宅しない事例が多々あります。
鍵のかかる扉のない平安時代の建物であれば、なおさらのこと。視点を変えると、戸締まりできない当時の建物で猫を飼うには、昼夜を問わず警固する人員を配置している家屋である必要があったのではないでしょうか。つまり、天皇やそれに類する資力を備えた者でなければ、現代のような感覚で猫を飼うのが難しかった、と考えることもできましょう。
一条帝の行動は、「うちのかわいい猫に何をする」というレベル感ではなく、「命婦のおとどがいなくなったら、どう落とし前をつける気だ」という気持ちの表れ、と見れば無理もないものといえます。『枕草子』が伝える名前のついた猫の話は、現代のような猫の飼い方が、当時の極々一部の人にしかできなかったこと示すものであると同時に、猫日記の宇多帝と同様に「1000年近く以前に存在した、現代人と同じような感覚で猫を飼っていた日本人」の記録と言ってもいいかもしれません。また、一条帝はこの逸話のほかにも、時の貴族の藤原実資の日記『小右記』にて「猫に対して産養の儀式を行うなんて、聞いたことがない」と、猫寵愛っぷりを非公開日記でdisられるという時代を越えた偉業も達成しているため、人間国宝ならぬ人間オーパーツ的存在を伝えるものと思われるのであります。
[Photo by ちゃわん]

猫の日本史 (歴史新書)
Source: 猫ジャーナル